STAP 騒動だとか小保方-笹井事件だとか云われているものは、マスコミにニュースネタを提供しただけなく、今も研究・開発の現場に影響を与えている。
この事件をきっかけに
というものが文部科学省で定められたからだ。
これを受けて国の研究関連予算の分配機関を中心に組織毎に研究上の不正に関する規定・ガイドラインを設けるようになった。
ネット上で窓口を設けているところも多い。
・問題となった組織を抱えていた JST (科学技術振興機構)。
・文部科学省直接にはここ。
・経済産業省管轄でも同様の窓口が新設された。
不正告発というわけではないが、各大学でも公益通報の窓口を設けている。例えば、京都大学はここ。
私自身は、国から大型の予算を直接受領したことは一度もないし、そもそも自分が純粋な研究者だとも思っていないが、分配を受けた組織で働いていたことは過去にある。ソフト開発などもやっている関係上、当局から関連領域の関与者とみなされたりもする。
そのせいか協力を求められている案件がいくつかある。主に資料提出要請だが、昨年(2018)は当局に直接出向いた。
こういった制度ができる前は、今でいう「不正」がかなりの頻度であったことは認識しているし、それで泣いた人も身近によくいた。
この制度の特に運用面に関しては言いたこともあるのだが、まずは、被害にあった人の無念のようなものが晴らされれば良いのになあと思う。
(追記)ところで、「研究不正」というとこのSTAP細胞事件を念頭においてコメントしている人が多いのだが、臨床研究ガラミで実際の臨床現場に影響を与えているのは、ディオバン事件とそれがきっかけで成立した『臨床研究法』の方だろう。
図式的に言えば、
基礎研究よりの不正ーSTAP細胞事件→ガイドラインの制定
臨床研究よりの不正ーディオバン事件→臨床研究法の制定
なのだ。
両者は、運用形態や対象とする範囲が違うし、そもそもガイドラインと法律では、強制力が違う。
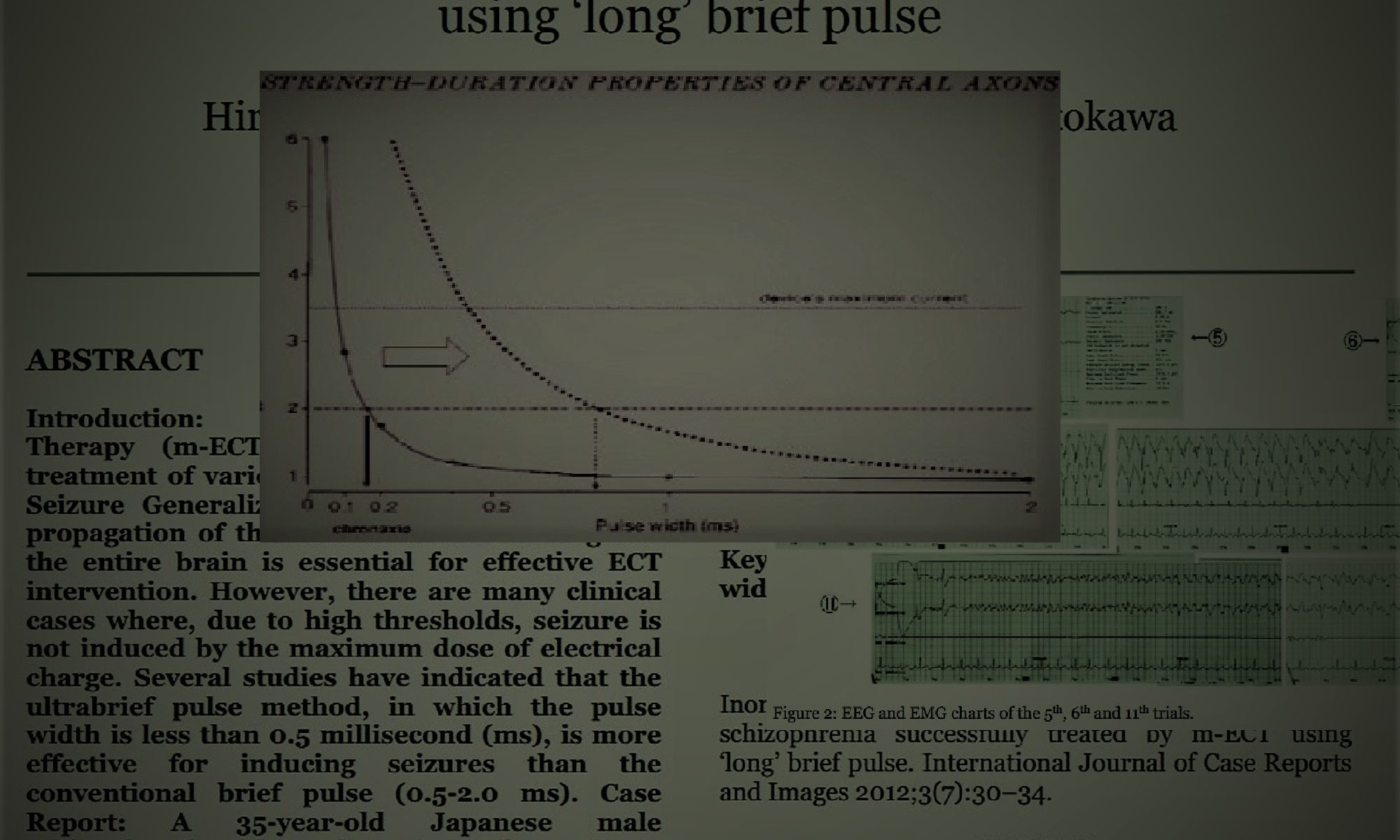

VISA林さんなんかは、これで挙げられるんでしょうか?
その呼び方はどうかと思いますが、意味は通じました。
たぶん、かっちりとした調査をやると問題になるのは、その人よりプロジェクトマネージャーや実際にソース管理をおこなった人になるかと思います。
総括的には、理念や目標は良かったが時期尚早すぎたとか、そもそも GPL 適用がまずかったのではないかとか、色々課題は出ているようですが、「前向きな形で解決したい」というような雰囲気は形成されています。
基本的なところで間違えているから、信用されなくなる。
http://archive.is/zZFU0
「fork(正確にはforkのforkのfork)してOpenOceanと名前を変えたプロジェクトを立ち上げた。」
正確には、 fork の fork ですよね?
そうです。
OpenDolphin2.7(LSC) → OpenDolphin-2.7m → OpenOcean
なので、fork の fork が正しいです。
ソースをざっとでも追いかけられれば、間違いようがないんですけどね。
増田氏、皆川氏も間違えて理解してましたよね?
私も以前はよくわからなかったんですが
A. LSC-増田ファクト(しばらく公開)-増田ファクト(プライベート)-消息つかめず…
で、現行の増田版 Dolphin は
B. LSC-PHAZOR/OpenDolphin-2.7m or OpenOcean -増田版 Dolphin
ですよね?
即レス。
A に関しては間違いなくそうですね。
かなり以前にプライベートリポジトリに移行しているので、分岐したもので公開されているものはないと思います。個人的に使っている人はいるかもしれませんが。
沖縄の会社/医療機関で使っていたところはあるようなんですが(メールもらった)、そこもけっこう改変加えていたようです。結局、そこも私らの OpenDolphin-2.7m 使いたいってことになって、乗り換えたようです。ちなみに、OpenDolphin-2.7m を github で公開していたのはそのためです。
B に関しては、ここでコメントすると色々問題ありそうなんで控えますが、公開順序でいうとそうなりますね。