今回は医療画像の fusion (一種の画像合成)のお話。
諸々の事情で MR(Magnetic Resonance 磁気共鳴)系の fusion を取り扱っていた。
なお、MRI って何?って方は、『MRI とは? -その1-』・『MRI とは? -その2-』・『MRI とは? -その3-』あたりをご覧ください。特に『その2』のスピンの説明はけっこう好評のようです。
しかし、MRI のプロトン密度強調画像程度でことが済んでいればいいんですが、この分野の技術進歩は速い。「拡散」強調(という撮像法。水分子の「拡散」というより「移動」といった方が正確なような気もしますが、ここでは慣例に従います)などは、以前より脳梗塞急性期の診断などに使われている。

上の画像は、脳梗塞の拡散強調像(DWI… Diffusion Weighted Image)です。拡散「強調」とは言うものの、実際に撮像するときは、移動しているプロトンからの信号を抑えるような工夫をするので、水分子が動きにくくなっている部位は、高信号になります。梗塞部位に含まれる水分子は、正常組織に比べ「動きにくく」なっているため、結果として梗塞部位は高輝度(白い)領域となって描出されます。
拡散強調画像は、基本 T2 強調画像をベースにしているので、本当に知りたい水分子の挙動(大抵の病変部で水分子は「見かけ」上、拡散しにくくなる。梗塞しかり、癌しかり)を取り出したい。このとき元の拡散強調画像より T2 などの影響を排除するため ADC(Appearant Diffusion Coefficient 「見かけ」の拡散定数) Map というのをつくる。
症例によっては DWI では異常を認めず、ADC Map で低信号(ときには高信号)となって描出されることがあるからだ。
水分子の拡散の度合いを知る上ではこの ADC Map は大変便利なのだが、その反面、組織のコントラストが普段見慣れているそれと違って形態などが読み取りにくい。ストレートに言えば「どこを見ているかわかりにくい」のだ。
この欠点を補うため、解剖学的な形態が読み取りやすい T1 強調画像に ADC Map を適宜「着色」した画像を重ね合わせると、医療者にとって「どこで何がおこっているか」直感的に理解しやすい画像が得られる。
一般に特定の情報を持った画像とそれとは別の情報を反映した画像を「位置を合わせて」合成して表示させることを fusion と言います。PET と CT の fusion はよく知られた例です。(参考:『PET/CT フージョン画像』)

今回は、T1 強調に ADC Color Map ともいうべき画像を fusion させたわけです。もちろん、HorliX 使いまくり。規格(DICOM)があることゆえ私一人では決められない問題もあったりするのですが、目処がたったらプラグインの形でまとめたいと思っています。
猪股弘明(精神科医、理学士)
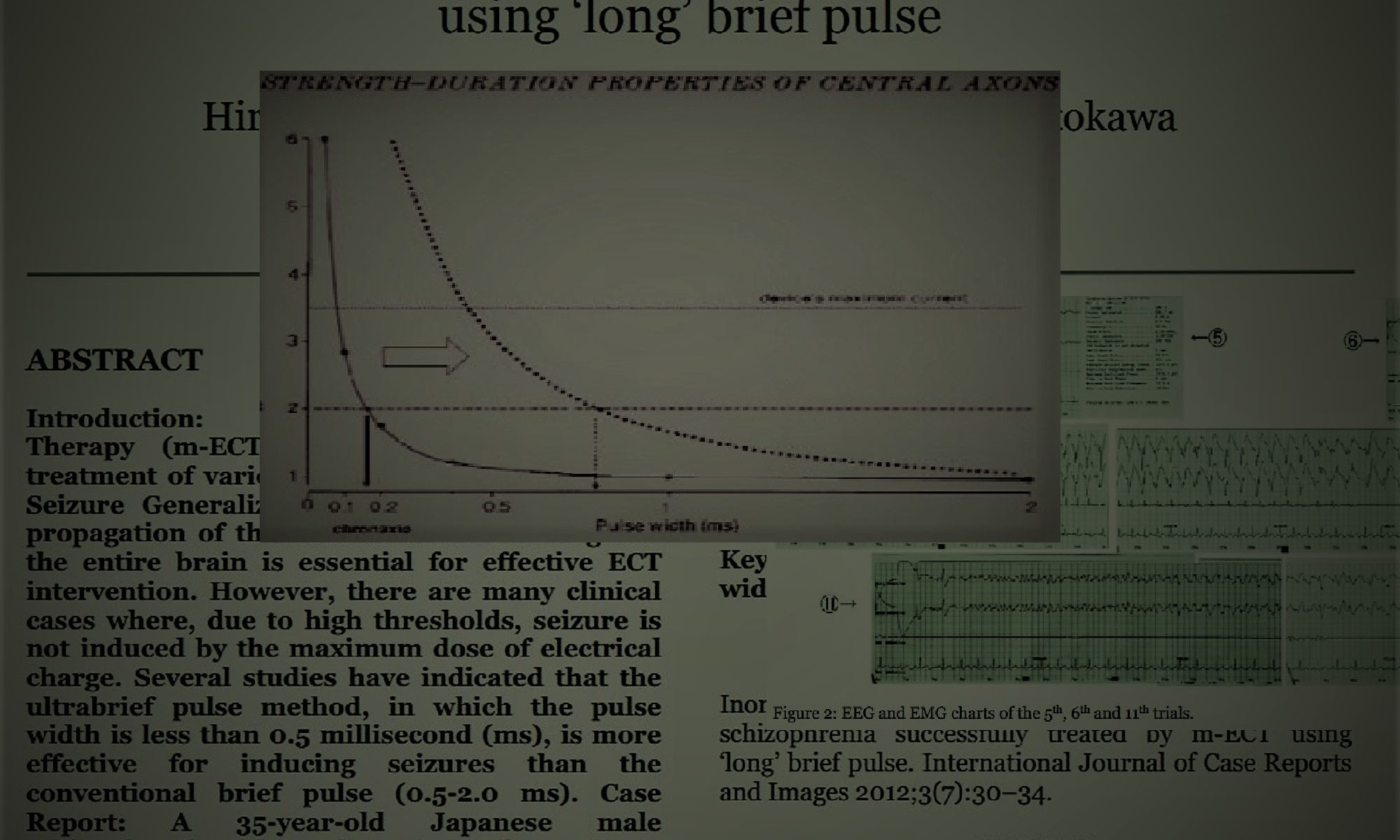

コメントを投稿するにはログインが必要です。